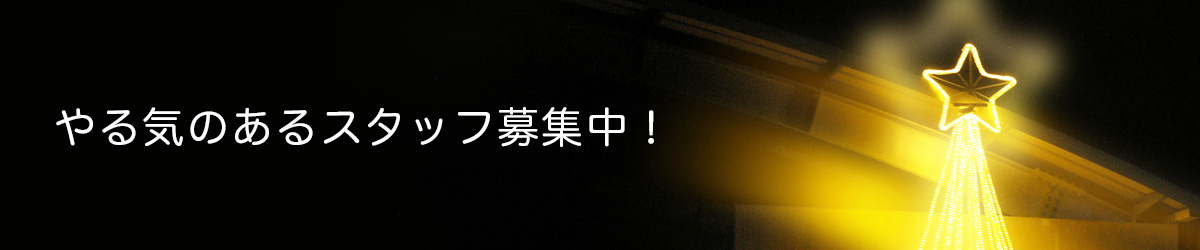わが町紹介 〜白石開拓物語〜
白石百余年の人々
片倉景範
白石開拓の功労者。天保9年5月仙台伊達藩の一支藩である白石藩主片倉小十郎邦憲の子に生まれた。
慶応4年5月、伊達藩は奥羽列藩に加盟し官軍に抵抗して敗れた。邦憲は職を失った多くの家臣のために北海道に新天地を求め、胆振管内登別市幌別地区の開拓を志したが、景範は父を助け幌別地区のほか白石、手稲地区にも旧家臣を入稙させた。最初、景範は幌別に住んだが、
のち白石に移り郡区制が施行された直後の明治13年2月に、豊平ほか四村の初代戸長となった。景範は戸長として治水事業の促進、農産物の増産など、村の発展の基礎づくりに努めて成績をあげた。同16年9月に退職故郷へ帰った。明治35年2月没。
佐藤孝郷
白石開拓功労者。嘉永3年3月白石藩の家老の子として生まれた。
本名治武右衛門孝郷、通称廊爾。武家の出身だけに曲がったことがきらいで剛直だったが、手腕は若いときから買われ常に人の先頭に立って大役をこなした。
奥羽列藩同盟が官軍に屈服した時、北海道開拓を思い立ち明治4年10月、藩士とその家族587人を率いて石狩入りした。11月から12月にかけ孝郷ら67人が白石に移り、粗末な小屋に住んで、雪中寒さと戦いながら死に物狂いで開拓の第一歩を踏み出した。岩村判官はその働きぶりに感嘆し「諸君の郷里の名をとって白石村と名付けよう」と沙汰した。孝郷は指導者として開拓の先頭に立ちながら、橋、墓、井戸などを次々と作った。学校も設けた。明治7年札幌町長兼白石雁木戸長を勤めた。
明治17年離道、大蔵省に勤めたが、大正11年1月17日、73才で没。
稲垣福松
地方自治活動功労者。明治27年5月、北郷開拓の草分け定吉の長男として白石町北郷に生まれた。
白石小学校卒業後、酪農に従事。温厚勤勉、敬神の念に厚く、非常に自己修養に精進した。
昭和8年から18年間、白石村会議員として地方自治の発展に尽くし、ことに戦中戦後、部落会長として部落民の指導に当たり、方面委員、白石産業組合、石狩産乳組合の理事、村農地委員会委員、村農業調整委員会長、北郷消防組頭など、多くの公職に携わり、地方自治の発展に貢献した。昭和35年5月24日没。
朝倉捨吉
地方自治功労者。明治29年1月白石村北郷に生まれ、白石小学校を卒業後、農業に従事。
性格質実剛健、進取の気性に富む。白石町青年団副団長、仏教青年会長、農事実行組合長、村農地委員会委員、北郷愛馬会長、村会議員、白石小学校教育奨励会長など、数かずの公職に携わり、
地域振興と産業の発達に尽くし、ことに馬匹の改良に大きな力をいれた。
昭和24年3月28八日没。