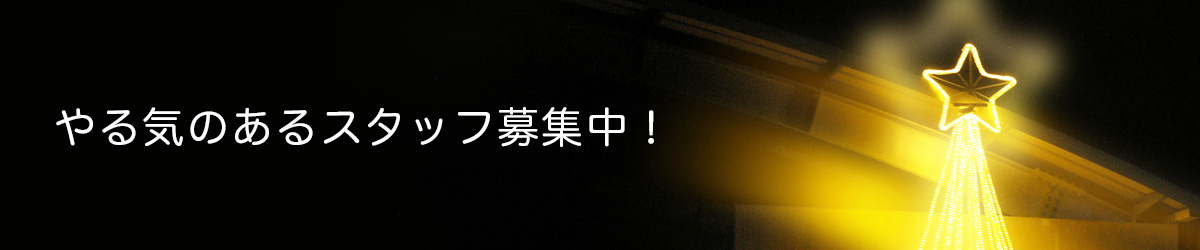わが町紹介 〜白石開拓物語〜
北海道に新天地を求めて入植の翌年、開拓の守り神として白石神社をつくった
入植の翌年、神社設置を願い出る

旧暦明治4年(1887)11月、仙台藩士族片倉小十郎の元家来たちが最月寒に入植し、懸命の努力で冬を越すための小屋掛けを終わらせた。場所は現在の国道12号の両側である。その努力を讃え、開拓使岩村判官は彼らのふるさとの名をとって白石村と命名したことは前述のとおり。
翌5年3月、白石村開拓使貫族取締助役・安斉謹吾、同・榊原次郎七、同取締・佐藤孝郷三人連署で、「入植して小屋掛けをして以来、今日まで開墾事業に励んできました。ついては、白石村の100間(180メートル)四方の土地に神武天皇を祭る神社を建て、日々の鎮守とすることに意見がまとまりましたので、許可してください」と開拓使開墾役所に願い出た。
これに対し開拓使は「神武天皇を祭ることは認めないが、村内に祠を建て、札幌神社遙拝所として敬うならよい」と答えた。

白石村民らは、開拓使仮本庁(今の中央区北六条東一丁目)近くから円山公園に遷座した札幌神社の旧社殿を譲り受け、その月に白石村百番地(旧五十番地)隣の予定地に移設して遙拝所ができた。
岩村判官は、旧白石藩士らが逆賊の汚名を着せられたまま新天地に移住し、天皇に忠誠を誓う姿にうたれ、お守りに持っていた畝傍山陵(神武天皇の陵墓)の砂を白石村守護産土神(守護神)として与え、開拓使属官(貫属)の高橋渉を別当(神寺を支配する職名)として派遣した。5年5月に鎮座祭を行い、以後この日を例祭日とした。
岩村判官の好意に感激した村民は、開拓使の指示による遙拝所としながらも、明治30年に晴れて白石神社と命名されるまでに、村内では陰で「神武社」と呼んでいた。
白石神社には専任の神職がいなかったため、神事の心得があった杉山順が明治30年まであたった。開墾のかたわら善俗堂で教育にたずさわり、公立白石小学校となった翌年の明治15年に学校を退職し、その後神官になっている。杉山順の死後、明治10年に幌別村から転入した阿部甚十郎が明治31年から勤め、畑は妻子に任せ、周辺地域の神社を回り、神事を行い、大正9年に没するまで勤めた。高邁な人格と立派な体格から多くの人に慕われた。
普段人の来ない村外れに神社を
白石神社を当時の白石村の最も奥に建てた理由は、古老座談会などで「入植時、一番地から神社のある五十番地まで約3キロメートルあった。村の集会などは善俗堂(白石小学校の前身)で行い、本府(札幌市街)へ出掛けることも多かったが、村の端の五十番地を訪れることはほとんどなかった。そこで、年に1~2回全村民が集う祭りが行われる神社は、一番不便な村外れに置くことにした」と語っている。
明治15年(1882)に社事代表の勝見直之は次の手紙を佐藤孝郷たちに送った。
「村の鎮守である神武天皇の社を建て、そのおかげで、お互いの家内安全、武運長久、開墾事業もうまくいき、いよい よ勤勉に励まれていることと思います。ついては、明治5年 に建てた札幌神社遙拝所が大破し、建て替えに必要な額が十円以上にもなるため、皆さんご寄付をお願いしたい。
これに対し佐藤孝郷は、「本社殿を修繕することはとてもよいことです。少額ですが一円を寄付しますので費用の一部にしてください。とのやりとりの手紙が残っている。
明治24年に懸案だった社殿改築を行い、明治30年(1897)9月10日、公式に念願の神武天皇を祭った「白石 神社」が誕生した。9月11日を例大祭と定め、明治5年に 決めた5月の祭と合わせて、春秋二回の祭が村民交流の場と なった。しかし、明治32年(1904)に社殿を火事で 失い、明治34年に再建された。大正9年(1920)に は村社に昇格し、大正14年(1925)には社殿を改築し た。社殿はこの後昭和41年にも火事で失い、翌年建て直して現在に至っている。